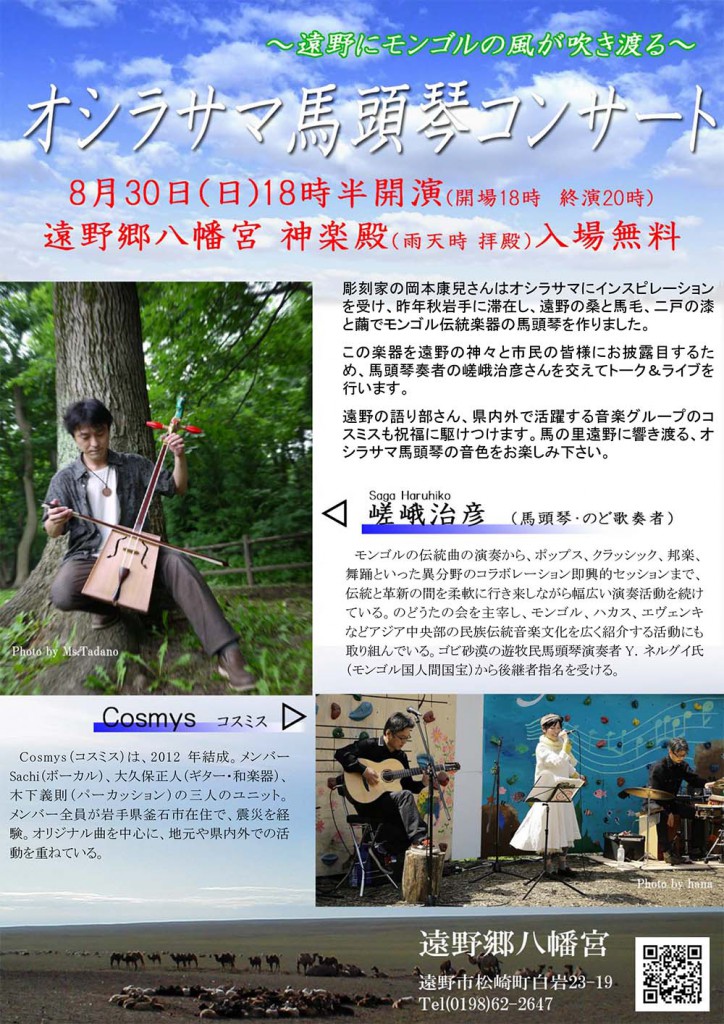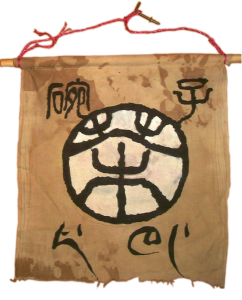『Mommy』という映画を知り合いが見て奨めてくれたので、観に行ってきた。
人物描写の多い映像なので縦横1:1という画面にも違和感はなく、むしろ登場人物たちの持つ精神的閉塞感をよく表していると思った。途中、二度ほどワイドスクリーンになる。初めは少年の心が開放され、平穏な時を満喫している場面。次は切羽つまった母親が少年を病院に引き渡す直前、一瞬浸る「良き時代」の回想と妄想。狭広ふたつのアスペクト・レシオの対比や切り替えも破綻はない。
しかし画角の狭さは両刃の剣で、ストーリーの展開とともに発達障害を持つ少年の行動や心情に僕の感情が同期するにつれて、狭められた視野にどうしようもなく居心地の悪さ、もっと言えば閉所恐怖症のような不安感を持った。もっとも、それがこの若い監督グザヴィエ・ドランの狙いだったろうから斬新だけども非常に効果的だと言える。
何十年も前のことだが、全く異質な映画で 『Stalker』(監督A. タルコフスキー)という映画を観たとき、友人が「こんなに居心地の悪い、楽しくない映画は初めてだ」と吐き捨てるように言ったのを思い出す。チェルノブイリ原発事故サイトを想起させる(といっても映画は事故より以前の作品だが)立入禁止区域「Zone」の廃墟を延々と這いずり回るStalkerたち(今どきの「ストーカー」とは全く異なる意味)が感じたであろう或る種の絶望感でさえ、その時の僕は映画でしか味わえない非現実の疑似体験として、快感とは言わないまでも楽しむことができた。僕はさも分かった風に「非日常を味わえる良い機会じゃないか?」と怒る友人をたしなめた。
ちなみに彼は原子力工学科に身を置く大学院生で、且つ被爆二世だった。彼の置かれた環境や背負った運命の重さを僕は知っているつもりだったけれど、理解していなかったから脳天気なことも言えたのだ。その後のチェルノブイリ、福島の原発事故を直接ではないにしろ経験してしまった今『Stalker』を観直したら、僕もあの時の友人の気持ちになるかもしれない。
さて、『Mommy』で感じた不快感、不安感も、単に画面のアスペクト・レシオによる視野の限定というテクニカルな効果によるものばかりではない。少なくとも僕にとっては、少年期のADHDによる(軽度ではあったが)社会不適合で味わった疎外感や閉塞感、焦燥感それに怒り、という昔の僕自身のリアルな体験が底にあって、劇中人物と引いては映画そのものに感情投影をしてしまった結果なのだろう。劇中で少年がキレるシーンでは鼓動が早くなり目眩がした。席を立つか、さもなければ声をあげてしまうのではないか、とさえ思った。(一緒になってキレてる?)
いたたまれない中で、かろうじて救いだったのは、隣の席のオッサンがずっと居眠りしていたこと。目の前のスクリーンでは退っ引きならない状況でも、幸せそうにイビキをかいているのを横目で見ると「現実」に引き戻されて、少し安堵するのだった。(映画の、あのワイドスクリーン状態!W)
この映画を奨めてくれた知り合いもまた、僕とは違った意味で、つまり仕事で発達障害や適応障害と日々かかわっていて、職場で難しい若者たちへの対応を迫られブータレてることもある。はたして、映画館の観客も何かそれ風の人ばっかりに見えた。しかも、満席に近かったなあ、、、