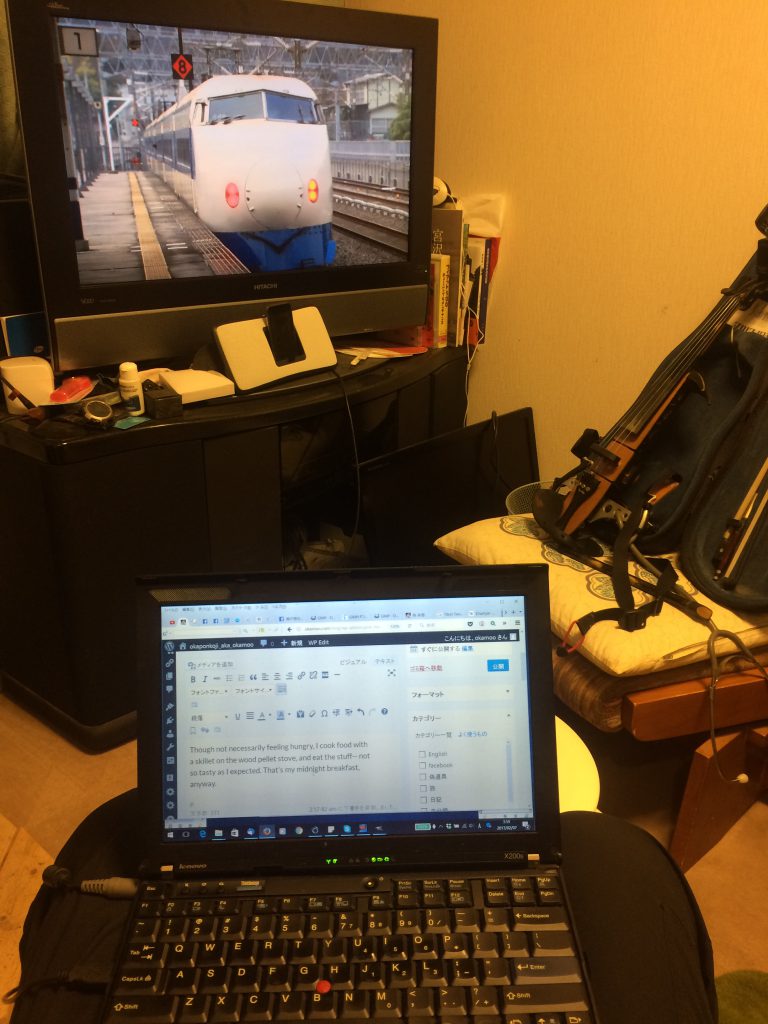五辻の「ひだまり」がひっそり閉店していた。それも昨年末に。
何年か前、お気に入りだったカイラス食堂の閉店に尋常じゃないショックを受けた。あの時は友達と店のガラスに張られた「ありがとう。カイラス食堂」という別のお客のメッセージを見て、すぐには閉店していると気付かなかった。家に帰って胸騒ぎがしてネットで調べて初めて、もうあのまったりした時間と空間は戻らないんだなと、、、。その遅発性の喪失感はただものじゃなかった。
カイラス食堂の前を通りかかり店が開いてない事に気づいたけど、きっと気ままなお休みを取ってるんだろうと僕はそのまま車を走らせた。一緒にいた遠来の友人が「なんか紙が貼ってあって、気になるから戻ってください」と言い、ぐるっと回って先の謎の張り紙を見つけたんだった。
さっきその友人から東京から「ひだまりを京都に行った友達に紹介したけどその人は見つけられなかった。ちょっとイヤな予感がするので見てきてほしい」との連絡があった。
彼の予感は当たっていた。見に行くまでもない。ネットにはいくつかの情報が上がっている。
https://webgram.co/p/BPojX46A3P1
すぐに件の友人にメールを書いた。また時を置かず返事が来た。彼は僕たちのお気に入りの店がどんどん無くなっていくことを嘆く、「次はどこで寛いだらいいのか」って。
カイラス食堂のときも、今回のひだまりも、その友人はたまたま京都に来ていて閉店のほんの一週間かそこら前に、僕も一緒に「いつも通り」のんびり、だらだら、まったりをキメこんでいた。鉄道の廃線や列車の廃止に群がる葬式テツみたいなことはしたくないが、、、終わる前に行けてよかったのかも。。。いや、そんなこと慰めにもならないな。。。やっぱりショックだ。
カイラス食堂、タコ焼六ちゃん、ともゑ食堂、みたらし団子の日栄堂、西大路のうどん屋台、、、喫茶静香は再開したけどおばちゃんは施設に入っちゃったし、、、そんで、今度はひだまり。。。どんどん滅びていく。
中でもカイラスとひだまりは別格に寛げた。ほんとに、次はどこへ行ってダラダラしたらいいんだ。。。