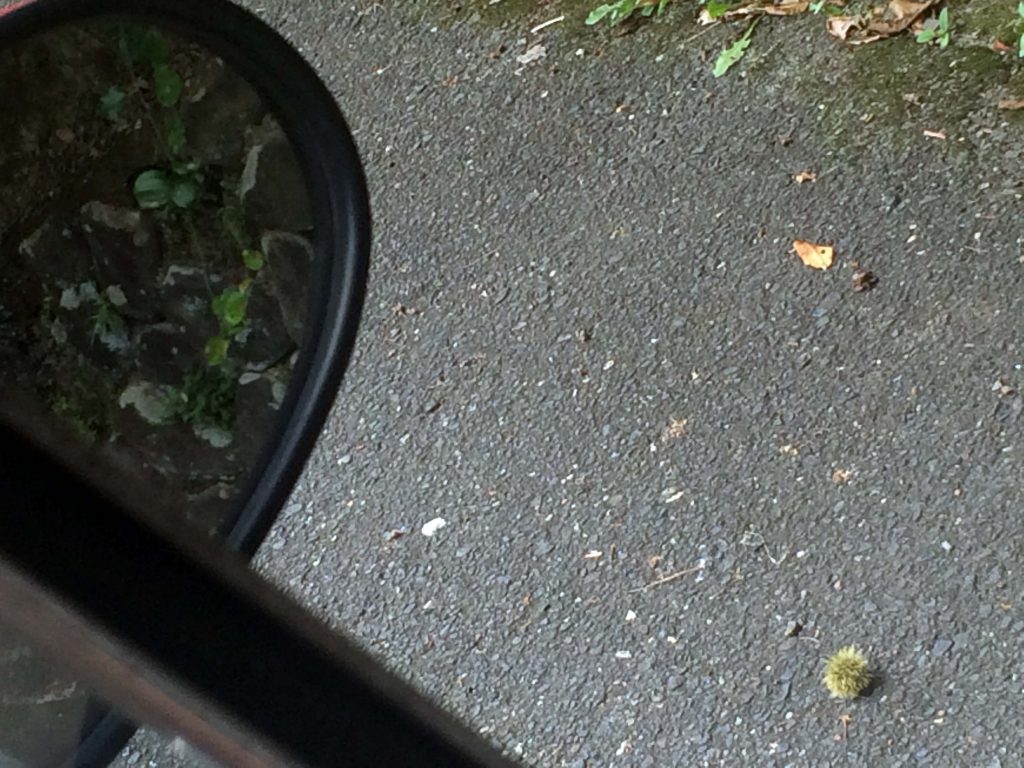ロシアのへんてこりんな小説が事実として受け止められていることを先に批判的に書いたんだけど、非科学的なことを言う人が嘘つきだと言っているわけではない。ただ、解らないものは解らないとしておくのならまだしも、説明のつかないような話を「適当な」科学用語を使って事実であるかのように言うのはとても受け入れられない。僕自身、科学的な説明のつかない経験はいくらでもあるが、それは自分の知識が足りないからだと思っている。また、心の内なる世界が外界の数学で記述できたり物理で説明がつくはずもないので、その境界線ではいつも悩ましく思っている。そのことで想い出す人がいる。
ジョージ・クレイマーは大学院で気ままな僕を拘束せず「放し飼い」にしてくれた指導教授で、後の作品の発想に自由度を与えてくれた恩人だ。
彼が亡くなって10年。今も彼との最初の出会いを鮮明に想い出す。僕は初め、長髪ヒゲ面で木こりのような風体のジョージが誰か知らず、ビル管理の用務員さんだと思っていた。そのまま彼にマディソンの街なかにある小さなウォルデン・パークに連れて行かれて、草ぼうぼうの小道の傍にある『In Wildness Is the Preservation of the World(野生にこそ世界の救い)』という 看板の前で、小枝にたかるアリとアリマキを見せて「こいつらは何だか判るか?」と言う質問をされた。
どうやらそれは僕を「量る」試験だったようだ。質問の答えはたまたま知っていた。「Aphid(アリマキ)」という単語走らなかったが、アリはアリマキを外敵から護り、アリマキは甘い分泌液をアリに与える、という共存関係にあるという僕の説明に、ジョージは満足そうだった。
ジョージはアメリカ先住民の血を引いていて、その精神性を受け継いでいると自負していた。その反面、80年代の初、中期、まだMacもWindowsも無い頃にコンピュータアートを始めていて、自動車や電子機器についての造詣も深く、アメリカというテクノロジー社会の申し子のような人でもあった。ときたま、僕のスタジオでの(形式上は)作品批評のディスカッションや、フランク・ロイド・ライトの旧邸だったという彼の家に招待されて食事しながら広範囲で豊富な話題の会話を楽しんだものだ。指導教授のジョージから「何の指導も受けず、何も習わなかった」けど、今の僕を作った重要な教師のひとりだと言える。
残念ながら、未だに僕の中で彼のような精神性と科学技術の融合とか調和は達成できていないので時に思考に矛盾が生じる。そういう時は手元にある彼の教員インタビューのビデオを観返して冒頭の言葉を噛みしめている。
I am a part Native American and uh… my grand mother was uh… my mother side was full blood.
And uh… m… of the first things I remember, when I was about two and a half, three years old, she took me out to the woods and had me hold onto a tree while she left and she would not come back until I knew the name of that tree: the tree’s name, not the scientific one but the name of the individual tree…
And so uh… what I learned was that you should allow the knowledge that you have built into you to come to the force, then there is a rightness to the work.
私はアメリカ原住民の混血で、、、祖母は、、、母方は生粋だった。
それで、、、 先ず最初に思い出すことのひとつなんだが、二歳半か三歳のころ、祖母に連れられて森へ行き、彼女が離れている間、一本の樹に抱きついている よう言われた。そして私がその樹の名前、学問上の樹木名ではなく、(個人の姓名のような)その樹固有の名前が判るまで彼女は戻ってこなかった。
つまり、、、 私が学んだのは、自分の中に自ら組み込んだ知識を発露させ力と成すべきであり、それでこそ作品に真実が宿るということだ。